

HOME > 岩船自慢
岩船自慢

― 岩船町 ―
岩船町(新潟県村上市岩船地区)は新潟市から車で北に60分ほど。
日本海に面し、およそ千戸の家が立ち並ぶ、歴史のロマン香る古くからの港町です。

― 日本書紀に残る地名 ―
どれくらい古いのかは誰にもわかりません。
日本書紀(720年成立)には、大化4年(648年)天皇の命によって磐舟柵(いわふねのき)が築かれたと記されています。柵とは、蝦夷に対する当時の大和王権の前線拠点だったと思います。
石船(いわふね)神社の社伝では、柵が築かれたとき、すでに石の祠が祀られていたと伝えていますので、それよりずっと以前から人が住んでいたのではないかと思います。
町の北側の浦田山丘陵では、6世紀前半に造られたと推定される石室がいくつか発見されています。それらは権力者の墓で、磐舟柵が造られる以前から、この地に小国家ともいえる集落が存在していた証拠です。
― 海で栄えた町 ―
現在、町の東側には美田が広がっていますが、かつては岩船潟(琵琶潟)と呼ばれる湖沼地でした。古い時代には、山形県の置賜地方から日本海に流れ出る荒川の河口に出来上がった、天然の良港だったのでしょう。
日本書記、斉明天皇の条にある「越の国守阿倍比羅夫が蝦夷征討のため百八十艘の軍船を率いて出発した」のは、岩船潟からだった可能性が高いと思われます。
中世から近世にかけて、荒川の水運を利用して集積された米やそのほかのさまざまな産物は、岩船の港から西へ東へと積み出されて、廻船業や漁業を中心に町は栄えました。
昭和29年に町村合併して村上市になるまでは「岩船郡岩船町」でしたが、郡の名は岩船町が古くから地域経済の中心的存在だったことから名付けられたのだと思います。

― 石船(いわふね)神社 ―
 港を見下ろす小高い丘に鎮座する石船神社は、延喜式神名帳(927年成立)に磐船郡八座の筆頭に記されている古社です。創建年は不詳ですが、大同2年(807年)、北陸道観察使・秋篠朝臣安人が下向のおり、京都貴船神社より貴船明神を勧請して社殿を建立したと伝えられています。御祭神はニギハヤヒノミコト、ミズハノメノミコト、タカオカミノカミ、クラオカミノカミの四柱の神様ですが、ミズハノメノミコト以下の三柱は貴船明神の神様で、ニギハヤヒノミコトはそれ以前から祀られていたと思われます。
港を見下ろす小高い丘に鎮座する石船神社は、延喜式神名帳(927年成立)に磐船郡八座の筆頭に記されている古社です。創建年は不詳ですが、大同2年(807年)、北陸道観察使・秋篠朝臣安人が下向のおり、京都貴船神社より貴船明神を勧請して社殿を建立したと伝えられています。御祭神はニギハヤヒノミコト、ミズハノメノミコト、タカオカミノカミ、クラオカミノカミの四柱の神様ですが、ミズハノメノミコト以下の三柱は貴船明神の神様で、ニギハヤヒノミコトはそれ以前から祀られていたと思われます。
明治になって、全国の神社の社格が定められたことがあります。新潟県内では越後一宮である弥彦神社が官幣中社とされましたが、石船神社はそれに次ぐ格式として県社に列せられました。
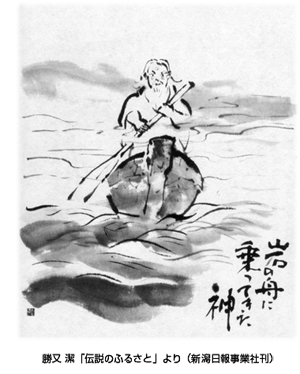
― 岩船伝説 ―
ニギハヤヒノミコトは岩の舟に乗ってこの浜にたどり着いた…
町にはそんな伝説が言い伝えられていて、だから町の名が「岩船」になったのだと言われています。
神様はみすぼらしい旅人のお姿をして一夜の宿を乞いましたが、初めに訪れた裕福な家ではその姿を見て、にべもなく断りました。次に訪れた貧しい家では「ちょうど今、お産が始まるところですが、よろしければどうぞお泊りください」と暖かく迎え入れました。その後、宿を断った裕福な家は家運が衰え、旅人を迎え入れた貧しい家は栄えたと、昔話は伝えています。
そのため、一般に神事ではお産を忌むとされますが、岩船の神様は嫌わないのだとか。
心優しい昔話を伝えながら、岩船では今も昔と変わらず時間がゆっくりと流れています。

― 岩船祭り ―
石船神社の例大祭である岩船祭りは、神様がこの町にお着きになられた縁日とされる10月19日に行われます。
神社の御神輿を中心に、各町内自慢の「おしゃぎり」と呼ばれる豪華な祭礼屋台9台が行列を作り、丸一日をかけて町を練り歩きます。
新潟県の無形民俗文化財にも指定されている岩船祭りは、町の歴史とも相まって古いしきたりを残すお祭りです。
お祭りにはそれぞれの家で家紋の入った門提灯を玄関に提げ、紅白の幕を張って祝います。家々ではごちそうをふんだんに用意して、祭りに参加している人には誰でも酒肴が振る舞われます。
祭礼行列の先頭を行く岸見寺町のおしゃぎりには、神様が乗ってきた舟を模した思われる明神丸が飾られますが、町の人たちは「お舟様」と敬い、信仰の町岩船のシンボル的な存在です。
岸見寺町には「木遣り唄」が伝えられていて、祭りの中の寿ぎの場面で披露されますが、岩船では「木遣りを歌う」とは言わずに「木遣りを上げる」と言います。これも木遣りの声そのものに神が宿ると考えられているからで、音頭を取る「木遣り上げ」の衆は羽織姿で幣束を手に厳かに木遣りを上げ、町の人は頭を垂れてありがたく木遣りを受けます。
岩船祭りに限ったことではありませんが、文章ではその魅力が十分に伝わりません。もし興味を持ったとしたら、岩船の誰かと友人になって、ぜひ岩船祭りに参加してみてください。

― 千二百年祭 ―
石船神社の創建は不明ですが、貴船明神を勧請して社殿を建立した807年を起源として、平成19年(2007年)に氏子会として「御鎮座千二百年奉祝行事」を、また町民側からの発案で「越後岩船千二百年祭」を盛大に挙行しました。5月5日の祝賀行事では、御神輿と9台のおしゃぎりによる祭礼行列が岩船港まで巡行され、御旅所をしつらえた緑地公園におしゃぎりが勢ぞろいしました。
中でもハイライトだったのは、岩船伝説に因み、御神輿様を御座船にお乗せして岩船港内での海上渡御でありました。悠久の時を経て海をお渡りになった神様を、大勢の町の人たちは岸壁で手を合わせて拝みました。
町が栄えて百年後も二百年後もお祝いができるようにと、私たちは祈っています。

― 十二灯流し ―
陽数の重なる7月7日を祝う中国の節句の一つであったものが、日本に伝わって機織りの神事やお盆行事と習合して、七夕は地域によってさまざまな意味を与えられているようです。岩船では月遅れの8月6日に七夕が行われますが、お盆の祖霊迎えの行事として伝えられています。
各町内では、竹と葦(よし)や萱(かや)を材料に、長さ4メートル、幅1.5メートルほどの船「七夕丸」を作ります。各家庭ではマコモ(岩船ではガヅボ)で作られた馬を色紙などで飾り、馬の背には家の名前を書いたのぼりを立てます。
その馬を町内の七夕丸に取り付けて、8月6日の夜に海へと流します。西方浄土におわす祖霊に、馬に乗ってお盆には家に帰って来るようにと祈ります。
帆に見立てた12個の提灯を七夕丸につけて流すところから、「十二灯流し」(じゅうにどながし)と呼ばれています。
提灯の灯りを揺らしてゆっくりと沖へ向かう七夕丸を、町の人たちは波打ち際に線香を燻らせて、手を合わせて見送ります。
海に生きる岩船町ならではの、夏の夜の幻想的な光景です。

― 岩船港緑地公園 ―
岩船港に大きな野外ステージを併設した緑地公園が完成したのは、ちょうど石船神社の鎮座1200年にあたる平成19年でした。毎年7月には岩船商工業会主催の「みなとフェスティバル」が開催され、大勢の人で賑わいます。ステージではアマチュアバンドのコンサートやカラオケなどが行われます。
岩船には唄の上手い人が多く、カラオケは高レベルです。潮風にのどを鍛えた漁師町ならではと思われます。
公園に隣接して漁協の直売所が開設されていて、岩船港に水揚げされる新鮮な魚を販売しています。店員は漁師の奥さんがほとんどで、頼めば並んでいる魚を手際よくおろしてもらえます。

― 宝の島 粟島へ ―
岩船港は、日本海の孤島 粟島への定期航路の唯一の発着所です。島の住民は400人足らず、手つかずの自然の中で、自給自足に近い生活をしています。タイ漁が有名で、島に渡る観光客の多くは釣りがお目当てですが、都会の喧騒とは無縁の大自然にカルーチャーショックさえ感じるようです。
岩船町のお店(会員)を見てみよう
▼岩船町の最新情報発信中!
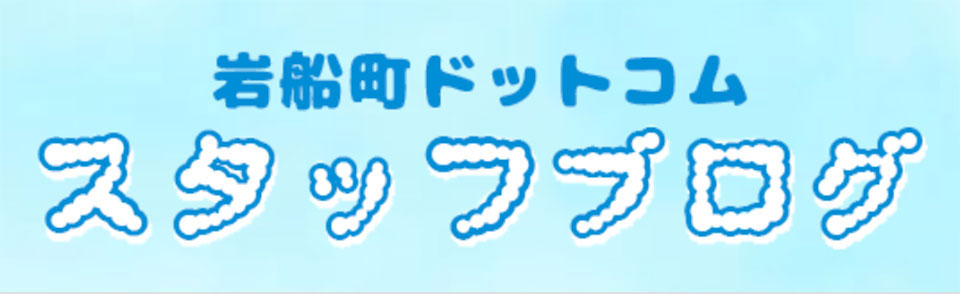
- 会員情報
- 会員企業さんからの商品紹介やイベント告知、お買い得情報のお知らせです。
- つり情報
- 岩船港の遊漁船や、砂浜・堤防からの釣り情報。釣りマニアスタッフの釣果自慢も!
▼岩船町ドットコムのInstagramはこちら!

